こんにちは!おてライターのHIDEさんです。お寺を楽しくする情報を発信しています。
さて、今回はお話をお仕事にされるすべての方へ勉強法を書いてみたいと思います。
大事なのは「まねぶ」こと
ぼくは時々ですが、人前で仏さまのお話しをさせていただくことがあります。
そのスタイルのことを「法話」といい、スタンダードなのが、次のような場面になります。
[su_note note_color=”#ffd366″ radius=”0″]お寺の法要や地区の追弔会
お通夜
法事のお経の後[/su_note]
お坊さんが法事やお通夜でお話をしているのはなんとなくイメージがあると思いますが、お寺の法要でのお話はもしかすると聞いたことがないという人も多いかもしれません。
実は、お寺の法要や地区の追弔会なんかでは、前席40分、後席40分という、一回約80分という長い時間をお話しさせていただくことが多くあります。
これがけっこう難しいんですね。長いだけならだれでもお話しはできますが、「飽きさせずに聞かせる」となると、なかなか思ったようにはいきません。
ベテランならいざ知らず、駆け出しのうちは原稿を作成したり、実演練習も必要になります。お寺にお越しいただくベテランの先生の姿にあこがれながら日々精進している毎日です。
そうやって試行錯誤する中でお話をする上で大事だなと思うのは「まねぶ」ということです。
この「まねぶ」とは、「学ぶ」の語源にもなったという説がありますが、先生たちの言葉や言い回しをまねして、自分のものにしていくということです。
学生のうちは何とか他と違うことをして目立とうという思いがあったりしますが、お手本を学ばずにいきなりオリジナルを披露してもいいものはできません。
それは、基本を学ばずに応用に挑戦しているようなものです。ですから、まずは「まね」が大事なのです。
何より大事なのは「聞く」こと
それでは、どうやって「まねぶ」かというと、それは何度もお説教を「聞く」ことで学んでいきます。
浄土真宗でも第八代のご門主である、蓮如上人の言葉に
ただ仏法は聴聞に極まることなりと云々。
現代語訳:…ただ仏法は聴聞するということに尽きるのである」と、蓮如上人は仰せになりました。
(第八代ご門主 蓮如上人御一代記聞書<193> 註釈版聖典 末 p1292)
と、あります。
「聴聞」(ちょうもん)とは、「仏法を聞く」ということですが、それに「極まる」とおっしゃられるほどに浄土真宗では「聞く」ということを大事にしています。
また、次のようにもおっしゃいます。
ある人が「法話を聞く場所では有難い尊いと思うのですが、その場を離れたらもとの心に戻ってしまいます。」と、自分の心のことを、まるで水を入れる籠(かご・ザルのイメージ)のようだと例えられた時に蓮如上人がおっしゃった言葉です。
その籠を水につけよ、わが身をば法にひてておくべきよし仰せられ候ふよしに候ふ。
現代語訳:「その籠を水の中につけなさい。わが身を仏法の水の中にひたしておけばよいのだ」と仰せになったということです。
第八代ご門主 蓮如上人御一代記聞書<88> 註釈版聖典 末 p1260
こちらもとても有名な言葉ですが、これは「自らの環境を仏法を聞くことのできる状態においていきなさい」ということをおっしゃっています。
つまりここから言えるのは、仏法を深く味わうには「自分の周りに、いつも聞く環境を作り出すこと」が大事であるということではないでしょうか?
それは、仕事に関しても同じで、自然と無理なく環境が整えばおのずと身についていくということになります。いつも繰り返ししている仕事は呼吸と同じように体が動くという人も多いでしょう。
文明の利器を積極的に使う
「聞く環境を作り出す」
一番いいのはお寺に出向き聴聞を重ねることですが、仕事もあるので、スケジュール的に難しいことも多々あります。
それに常に新しいものを聞く必要もありません。同じのを何度もという聞き方もあります。
そこで、活躍するのが、『ICレコーダー』です。
ぼくは自坊である賢明寺に来てくださった先生のお説教や、他のお寺に行った時に必ずICレコーダーで録音をするようにしています。
この方法はたいていの場合、最初の一回は自らお聴聞に行って録音することになりますので、それ以降は同じ録音を聞きたおすことで、「聞く環境を作り出す」ことができます。また、もちろん、聴聞に言った分だけデータは増えていきます。
しかし、録っておくだけで満足してはいけません。宝の持ち腐れになってしまいます。
ポイントは「繰り返し耳で聞くことのできる状態」にして活用していくことが何より大事になってきます。
生活スタイルに合わせることが大切
「繰り返し耳で聞くことのできる状態にする」とは、具体的には音楽CDにしたり、聞ける状態のデータにしたりすることです。
ただし、「聞く」ことに無理は禁物です。
CDプレーヤーの前に正座して、録音してきたものを聞く。これではおそらく数日も続かないでしょう。
学びのチャンスは机の前だけではありません。その状況が必要な時もありますが、もしそれだけが勉強の方法だと思い込んでいるなら、その場所と時間がとれないと学ぶことができないということになってしまいます。
では、どうすればいいか?
それは、「聞く」ことを日々の生活スタイルの中に自然に取り入れていけばいいのです。
最終的に「聞く環境を作り出す」ことが、大事なのですから、続かなくては環境たりえません。ですので、「無理なく長く続けられる」ことも押さえていきましょう。言うならば「ながら」ぐらいがちょうどいいのです。
ぼくの場合、「車の中で聞いて学ぶこと」がベストマッチでした。
どうして車で聞くことがよかったのか?
ぼくはお坊さんとして、月命日のお参りをします。
お宅に上がって仏壇でお参りしたら、車で移動して次のお宅へ…、ということを繰り返していきます。
移動時間が短いところもありますが、隣町へ行ったりする時は行き帰りで30分ほど車に乗っていることもあり、短い移動も合わせると車内にいる時間がけっこうあります。
そして月命日は日付(1日~31日)でお参りしているので、ほぼ、365日繰り返されることになります。
この時間がぼくの「学びのチャンス」でした。
ところが、この「車で聞く」というのがなかなか曲者だったのですが、それは次回に。
効果はどうだったの?
実際、繰り返し聞くというのは、とても効果があって、先生たちの口ぶりを楽しみながら真似していたら、いつの間にかお説教でも使えているということがありました。
これは、いわゆるスピードラーニング方式ですね。たぶんあの教材も効果あると思います。
そこから、自分のものにしてオリジナルに昇華していくのは、実演などの努力が必要ですが、話のベース作りには確実に効果があります。
まとめ
さて、いかがだったでしょうか?
今回は「法話」に焦点をあてた勉強法ということでしたが、お話をされることがあるお仕事でも役に立つのではないでしょうか?
気になる人のスピーチや講演、またはテレビの音声などを録音して、自分にあった環境で繰り返し聞いていくことができれば、楽しみながら学ぶことができるはずです。
ポイントをまとめてみると…
[su_note note_color=”#ffd366″ radius=”0″]
・オリジナルの前にまねて学ぶ
・聞く環境を作る
・ICレコーダーを使う
・生活スタイルに無理なく取り入れる
[/su_note]
…ということになると思います。
順序でいうと、「生活の中に聞く環境を作り、まねする」という流れになりますね。
ぜひ、取り入れてみてくださいね!
——————————-
「聞く環境を作る」具体的な方法はこちら↓

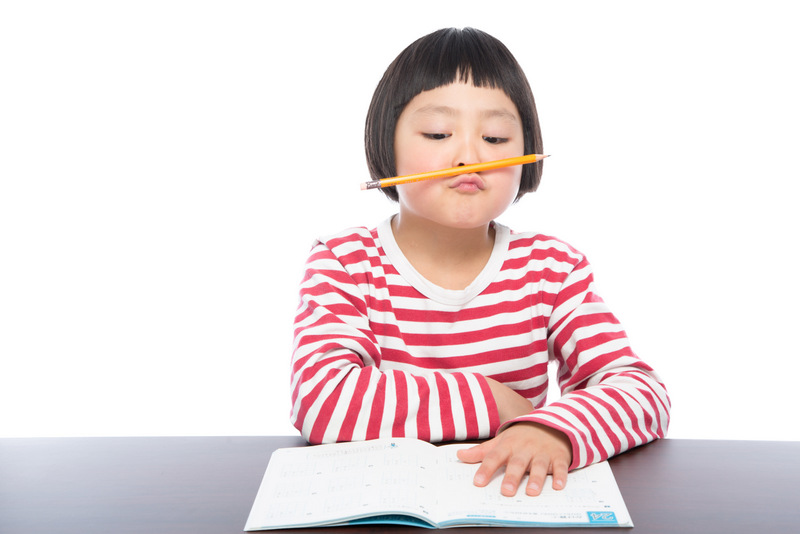
コメント