博多駅に行くと引き寄せられるように入ってしまう店がある。
おしゃれな雑貨店という感じだが、洋風ではなくて、和の雰囲気が似合う店内。
小物やカバン、服も置いてあり、女性に人気。
お店のロゴには鹿のマーク。
さて、このお店の名前は…と、
クイズのようになってしまったが、
そのお店の名前を中川政七商店という。
博多駅で言うと、アミュプラザ(東急ハンズが入っているところ)とデイトスという
直線距離で100メートルあるかないかの所に、2店舗も出店している人気のお店だ。
ホームページには、次のようにある。
■中川政七商店は奈良の地で享保元年(1716)に創業いたしました。
創業以来、手績み手織りの麻織物を扱い続けております。
近年は工芸をベースにしたSPA業態を確立し、全国に直営店を展開しております。
創業300年以上!
元々は麻の織物のお店であるという中川政七商店。
それが近年になって、私たち消費者から見れば、
工芸をベースにしたおしゃれなお店になっているとのことだ。
注)ちなみに、SPA業態とは…
SPAとはSpecialty store retailer of Private label Apparelの略で製造小売ともいう。
企画から製造、小売までを一貫して行うアパレルのビジネスモデルを指す。
消費者の嗜好の移り変わりを迅速に製品に反映させ在庫のコントロールが行いやすいなどのメリットがある。(コトバンクより)
身近なところでは、ユニクロのような企業を指す言葉のようだ。
おしゃれな奈良ブランド
話を戻そう。
このお店の商品を初めて見たのは友人の結婚式で行った奈良でだった。
たまたま入ったおしゃれなカフェ雑貨店で「鹿の家族シリーズ」の刺繍を見た覚えがある。
結局、その時買ったのは、BAN INOUEの鹿の可愛いストラップだったけれど。
(注:BAN INOUEの創業者夫婦の奥さんの方は、中川政七商店がご実家で現社長は甥にあたるそうです。へー!!)
でも、その刺繍の印象は強く残っていて、
奈良っておしゃれなんだなと思うきっかけにもなった。
もはや、これは紙上コンサルティング
前置きが長くなったが、そんな中川政七商店13代目の社長さん、
中川淳さんが書かれたのが今回の本、『経営とデザインの幸せな関係』だ。
この本を読むまで、中川政七商店は、
女性向けの和の雑貨店というイメージだったが、
「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、
製造・販売を手掛けるのと同時に、工芸業界の再生コンサルティングも
手掛けているのだそうだ。(今回、読んで初めて知った!)
実は、ぼくたち浄土真宗の僧侶に馴染みの深い、
あの薫玉堂さん(西本願寺前にあるお香屋さん)も
コンサルティングしてもらっているのだ!!(これも、初めて知った!!)
さて、本書の内容だが、大まかな内容はビジネス実践書になっている。
しかし、まあ、これが面白いのだ。
この本を一言でいうと、
「ものづくりから販売までを例とした紙上コンサルティング」と言えるだろう。
社長の経験に基づく理論と、フレームワークやシートを使って、
実際にこれまで企業におこなってきたコンサルティングの
具体的例を示しながら、ページが進んでいく。
コピー機などで拡大すれば実際に書き込めるので、
使ってみるといいだろう。
ただ、始めは決算書など数字の話があったので、
ちょっと、「おぅ…」と構えてしまったが、
それは最初のうちだけで、すぐにのめりこんでしまった。
読み進めていくうちに気づいたのだが、
この本はものづくりに関わる人だけではなく、
様々な人に役に立つ知識が収められている。
例えばお寺の理念の制作や、
市民グループでの活動の方向性を決定することにも使えそうだし、
お家ワーク、自営業をされている方なんかにも十分実用性があるものだと思う。
もちろん、自分のしたいことを整理するのにもいいだろう。
おもしろかった事例
中でも面白かったのが、長崎県の波佐見焼のマルヒロという会社のコンサル事例で、
マルヒロが挙げた項目の中に、強みが見いだせなかったため、
自社の定義を変えるというアイディアを選択したそうだ。
当初「自社=マルヒロ」としていたが、もう少し広い範囲で見ることにし、
「自社=波佐見という生産地」という定義づけをした。
このことによって、他産地と戦える強みを見出すことができたと記されている。
つまり、近くの同業者がライバルではなく、
他地域の産地が本当のライバルだったということだ。
なるほど。冷静によく考えてみると、こういうことも見えてくるようだ。
その結果生まれたブランドが『HASAMI』というもので、
そこで生み出されたスタッキングできる
カラフルなマグカップが大ヒットしたらしい。
(最近、洗い物を手伝うので思ったのだが、
スタッキングできるマグカップって、収納時にめちゃめちゃ便利やん!!)
[amazonjs asin=”B004WJ7378″ locale=”JP” title=”HASAMI ハサミ ブロックマグ レッド 波佐見焼”]
共通言語を築くのにおすすめ!
特に本書をおすすめしたいのは、
チームで取り組まないといけない状況の方や、
そのリーダー的ポジションにいる方たち。
一人ならいざ知らず、数人で何かのプロジェクトを進めていこうと思うと、
必ずと言っていいほど、齟齬が生じる。
しかし、この本に出てくるフレームワークやシートを使って、
やりたいこと、やるべき仕事を明確化、言語化し、
最終的にチーム内で“共通言語”を作ることができれば、
プロジェクトの生産性を上げることにつながるはずだ。
工芸業界に刺激を受けて…
本書を読んで思ったのは、
伝統があるから、これから先も残っていくというのはもはや幻想だということ。
これから先、生き残っていくには熱い思いや使命とともに、
時代に合わせつつも、時代に流されないそんな柔軟さが必要なのだろうと感じた。
それは言い換えれば、『伝統と革新』
使い古された言葉だけれど、やはりここに魅力を感じずにはいられない。
革新というと、古いものを全て刷新するイメージがあるが、そうじゃない。
本当の革新とは、全てをぶち壊すことじゃない。
伝統を受け止め、新しい感性で創造する、
『伝統に裏打ちされた革新』こそが、実は最強の武器なのだと思う。
まさにそれを地で行く会社が中川政七商店だ。
お寺界隈も危機感がつのるが、
工芸業界と同じように『伝統に裏打ちされた革新』で、
おもしろくなるのは間違いない。
この本に出てくる、スタッキングできる波佐見焼カップや、
パン切り包丁、ポンチョを欲しいと思うように、
お寺にぜひとも行ってみたいと思ってもらうこともできるはずだ。
そう考えると、うずうず、わくわくしてくる。
未来が楽しみになってきた。

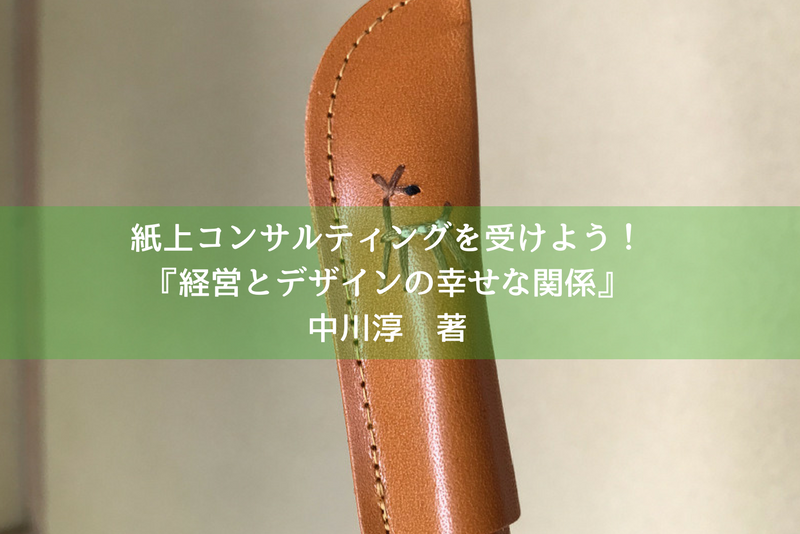

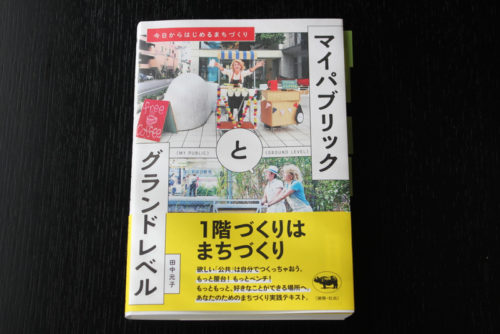

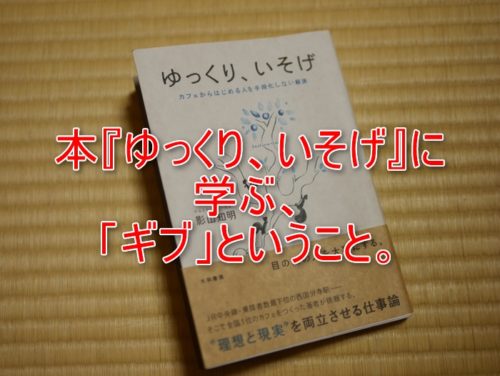
コメント