こんにちは!おてライターのHIDEさんです。
本はいいですね。本を読んでいると多くの言葉に触れることができますし、時折、キラッと光る力を持った言葉に出会うことがあります。
まるで宝物に出会ったような感覚で、ぼくはその瞬間が大好きです。
今回はそんな言葉の発見のお話。
部屋の整理をしながら、少し前の『ソトコト』を読んでいて、非常に興味深い言葉を発見できたので紹介したいと思いますね。
それではいってみましょう!
特集:本と、本がつくる場所 ソトコト 2016年12月号

この号は非常に興味深い特集で、特集タイトルが『本と、本がつくる場所』とあります。その特集につられて購入したわけですが、内容としては、「リトルプレス」や「独立系町の本屋さん」が特集されています。
ソトコト
[amazonjs asin=”B01M092S8B” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”SOTOKOTO(ソトコト) 2016年 12 月号本と、本がつくる場所”]
その中に、JR新潟駅から徒歩15分。『BOOKS f3』という、写真集を中心に扱う本屋さんが特集されていました。
このお店、写真でみるととても雰囲気がよく、元・時計店であったことをうかがわせる店頭のディスプレイコーナーがまるでアパレルのセレクトショップのように目を引きます。
セルフリノベーションをしたという店舗は木の温もりも感じることができ、とても入りやすい雰囲気を醸し出しています。
一度訪れてみたいなぁと思わずにはいられないお店です。
このお店のオーナーである小倉快子(やすこ)さん。カメラマンでもある彼女は故郷の新潟にお店を構え、本屋、ギャラリー、カフェの三本柱で地域に根差した場所を目指しているといいます。
佐藤さんのことば
『BOOKS f3』の小倉さんが出店の際に相談をした方で、同じ新潟市内で全国にファンを持つ『北書店』を営んでいる佐藤雄一さんという方がいらっしゃいます。
今回紹介したいのは、佐藤さんがソトコトのインタビューを受けて放った次の言葉です。
今や本を売るのは難しい時代で、右から左へと売れ続けるものでもない。本以外のほかのふたを開けていく必要がある。“まちにある本屋”ではなく“まちの本屋”であるべき
ソトコト 2016年12月号 p36
この言葉に衝撃を受けました。
なぜなら、最近ぼくが考えていることが、言語化された!と思ったからです。
特に、「まちにある本屋ではなくまちの本屋であるべき」という言葉は、そうだよなと、とても納得のいくものでした。
詳しくは語られていませんが、ぼくは次のように思いました。
まちにある本屋とまちの本屋の違い
[su_note note_color=”#ffd366″ radius=”0″]
①まちにある本屋
②まちの本屋
[/su_note]
以上の2つの言葉がでてきましたが、少しこの2つの言葉を味わってみましょう。
まず①つ目の「まちにある本屋」は佐藤さんが使われた文脈では、ただ単に物理的に本屋さんが存在しているということでしょう。
それは、大手チェーンでもいいし、『BOOKS f3』さんでなくてもいいということを表しています。
しかし、②つ目の「まちの本屋」というニュアンスになればどうでしょう。
微妙な言葉の違いですが、住民から頼りにされている「町になくてはならない本屋」や、「町のための本屋」という風な意味が見えてきます。
そこから佐藤さんは「まちにある本屋ではなくまちの本屋であるべき」と、おっしゃるわけです。
そこに、ぼくはなるほど!と思ったのです。
お寺に置き換えて考えてみよう。
そのことを、お寺に置き換えて考えてみましょう。
[su_note note_color=”#ffd366″ radius=”0″]
・まちにあるお寺
・まちのお寺
[/su_note]
いかがでしょうか?
先述の本屋さんのように「まちにあるお寺」と「まちのお寺」はずいぶんと印象が違います。もちろん、ぼくが目指すお寺は後者です。
賢明寺では、コミュニティや場所としてのお寺、また、信仰心・宗教施設としてのお寺を目指したいという2つの意味で、「人と心のよりどころ賢明寺」というキャッチコピーを個人的に作りました。
その意味合いは「まちのお寺」という言葉にピタリと重なります。
人と心のよりどころを目指して
「人と心のよりどころ」にお寺がなっていくということは、人々にとってお寺が、
・我がまちのお寺。
・私のお寺。
・私の居場所。
…というような意味になっていくことだと思います。
そういったお寺にしていくために最近、重要だと考えていることがあります。
それは、お寺側からの発想よりも、「周りの人のためにお寺ができることは何なのか?ぼくが役に立てることは何なのか?」ということを大事にしようということです。
お寺側からの発想では「こんなにしてるのに、どうしてこないんだ?」という上から目線や、「お寺に人がどれくらい来たか?(来させるか?)」という、成果主義になりがちですが、
そうやって結果を気にするよりも、まず目の前にあることを精一杯やることが大事です。
例えば、日々の法務を大事にすることを筆頭に、人が喜ぶ顔を想像してブログを書いたり、これはあの人だったら知りたいんじゃない?と相手のことを考えたり、楽しんでもらおうと思ってイベントを企画することなどです。
そこに、人が増えるというような結果がついてくるかどうかは、はっきり言って分かりません。
しかし、分からないことを考えるほど意味のないことはありません。
ですから、むしろ集中すべきは未来ではなく、今日一日。一点です。
今日の一日は、少しでも人のためになることができたか?
少しでも前に進むことができたか?
その積み重ねが明るい未来を作っていくのだと思うのです。
まちのお寺への道は一歩ずつ。ぼちぼちかつ、確実に歩んでいきたいものです。


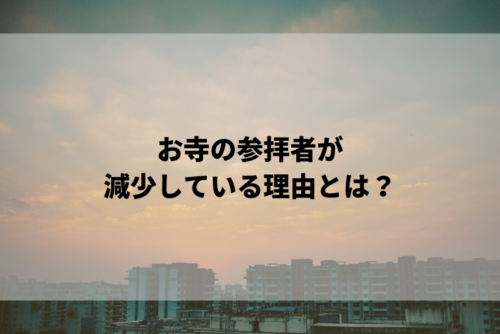
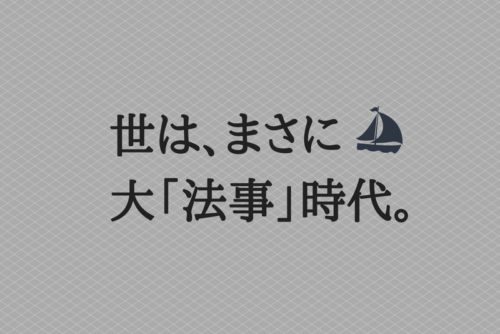
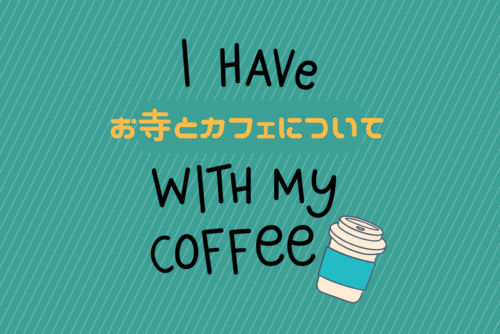



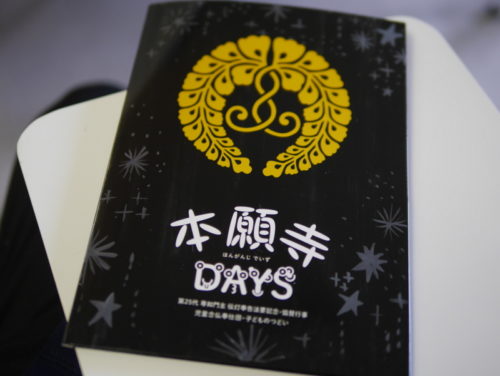
コメント