「若い人もお寺にお参りに来てほしいなぁ」
「過疎地ではなく、若い人もいる町なのに。どうしてお寺にこないのかなぁ。」
そう思っているお寺さんは多いと思います。
こんにちは!
おてライターのHIDEです。
お寺の楽しさ、お寺で役立つ情報を発信しています。
今回は、「若い人のお参りがない(少ない)問題」について考えてみましたよ。
若い人が抱える、心理的ハードル
さて、さっそくですが、質問です。
お寺というと、若い方が行くイメージですか?
それとも、年配の方が行くイメージかと問われたら、
あなたはどう答えるでしょうか?
これには、ほとんどの方が「ご年配の方が行くイメージ」
とお答えになることでしょう。
ただ、最近は全国的に若い人とのご縁づくりを目指す取り組みが行われてきており、
きっかけがあれば、若い人でもお寺に足を運ぶようになってきました。
若い人が「お寺自体に行く」ハードルは下がりつつあるといっていいでしょう。
しかし、それでも、「お寺の法要に行く」というのは、20代~40代の特に若い人にとって、
ぼくたち僧侶が思っている以上に、心理的ハードルが高いようです。
たいていの場合、ぼくたちは、若い人が法要・法座へ抱く心理的ハードルを
お経が難しいからとか、お布施のことが分かりにくいからとか、
お説教の内容が分からないからだ…などと、考えてしまいますが、
実は「もっと単純なこと」が心理的ハードルになっているのではないでしょうか?
そのハードルとは、『年齢差』です。
お彼岸フェスでの出来事
先日こんなことがありました。
賢明寺で、お彼岸フェスというものを開催した時のことです。
ちなみに、お彼岸フェスとは、お彼岸の認知向上と、
「お寺は楽しい!」ということを知って欲しいと思い開催したものです。
広報手段として、Facebookの利用と、簡単なチラシの作成をしたのと、
月参りの際に「この人にこのイベントはいいんじゃないかな。」
という人に、一対一でお誘いしました。
その中でご年配の方が反応を示してくださり、
「それは、楽しそうですね。伺います!」と、
参加してくださることになったのです。
しかし、実際その方が来てみると、30代~40代の若い方が多く、
その中に70代が一人という構図になってしまいました。
(上手く同じ年代の方をお誘いできなかったのが原因ですが…)
その方は若い人の中で自分だけ年が違うということをとても気にされていたようで、
こちらが、「大丈夫ですよ。若い方も上の世代との交流になりますから」
と言っても、「私なんかが、いいんですか?」
と、しきりに聞かれていました。
その後、月命日参りで、その時のことを伺うと、
「若い人ばかりだったですね。楽しかったですが、正直引いてしまいました。」
とおっしゃっていたのです。
このことがあって、もしかすると、
若い方がお寺の法要にお参りしづらい要因の中にも、
『年齢差』があるのかもしれない、と思い至ったのです。
人は「同じ要素」で安心する。
人は「同じ」であることに、ある種の安心感を感じます。
例えば、○○県出身で同郷、○○年生まれの同い年、
○○中学出身の先輩後輩、同性、同じ職業などなど。
初めて会う方であっても、
「同じ○○」というキーワードが出れば、
一気に打ち解けてしまうことがあります。
それは相手に自分と共通する何かを見つけたからであり、
それが安心感につながるのです。
しかし、お彼岸フェスの時はその反対で、
年配の方にとって、周りの人たちの
「年齢が」「同じ」ではなかった。
だから、不安になり、
居心地の悪さを感じてしまったのです。
再構築も視野に
お彼岸フェスの時は、若い人の中に年配の方が混ざった形でしたが、
これは、逆もありえます。
逆とは、年配の方が多く、若い人が引いてしまう状況です。
(あくまで、若い人をターゲットにした時の話ですよ。)
お寺的にはどちらかというと、こちらがスタンダードな状況です。
『年齢差』による「参りづらさ」は、
ぼくたちが思っている以上に
高い心理的ハードルになっています。
そこから考えると、若い方をターゲットにする時は、
従来の法要に来てもらう方法以外も視野に入れる必要があります。
形にこだわりすぎて、仏法を聞いてもらうという目的を見失っては、
本末転倒ですから、若い方に合わせた形の法要をもう一つ増やすか、
ゼロベースで再考・再構築した仏法伝道・聞法の場づくりを考えてもいいでしょう。
(再考・再構築という意味では、
今年の2月に京都、3月に富山で行われたスクールナーランダが参考になりそうです。)
とにもかくにも、これからは、お寺からの押しつけではなく、
僧侶・お寺として、どうすれば人の役に立てるかを考え、
行動することが若い人との縁づくりになっていくことでしょう。


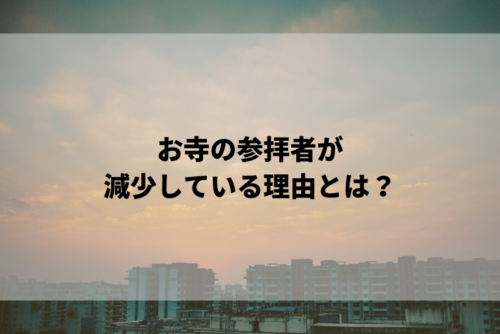
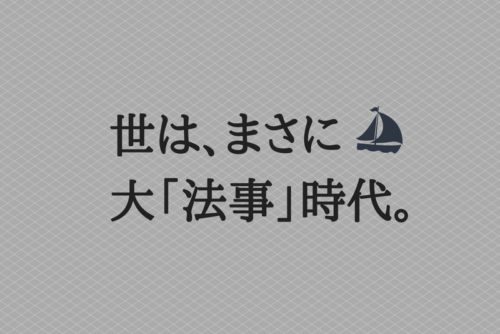
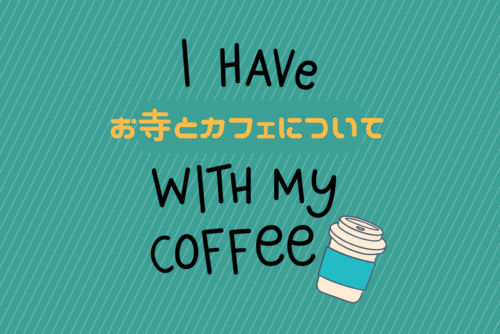
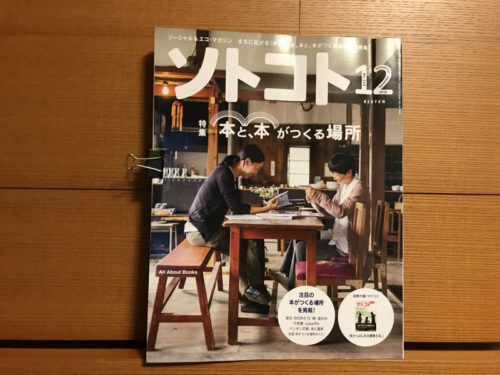


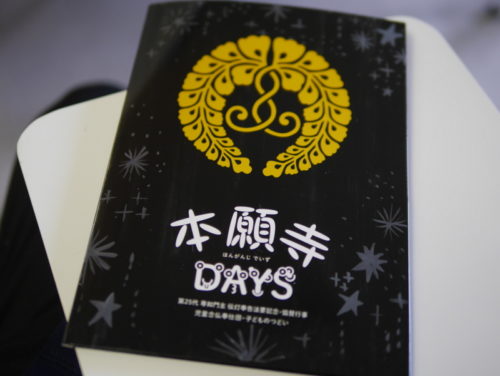
コメント