
子どもの頃の話。
「帰省する」「田舎に帰る」というのが羨ましかった。
なぜなら、ぼくのばあちゃんは近いところに住んでいたからで、車で10分もかからない距離だったから。
ばあちゃんに会えるのは嬉しかったが、旅行気分にはなれなかったのだ。
だから、そういう経験できないことが羨ましかった。
それともう一つ、「親戚の法事があって…」と言って部活を休むヤツ。
これもなぜか羨ましかった。
ある時、同級生が学校にギブスをした松葉杖で来た。
「どうしたんだ?」と聞くと、「足が痺れて立つ時に足をぐきっ!とやっちゃった。」という話をしてくれた。
本人は不自由そうだったが、法事の光景が浮かび、なんだかにぎやかそうな、独特の空間にあこがれたものだ。
お寺だから法事なんてしょっちゅうやってるんじゃないの?と思うかもしれないが、そんなことはない。
家がお寺でも、小さい頃に親戚の法事に1回行ったかどうかぐらいだ。
しょっちゅう行っているのは住職ぐらいで、それも門徒さんのお宅の法事だ。
そこに寺の子がお参りにいくわけでもないし、他人の法事に参加者としてひょっこり顔を出すわけにもいかない。
そこで、今のぼくは思った。
もしかすると、法事に参加したことがない人もいるんじゃないだろうか?
法事にあこがれ続け、こっそりと「一人法事ごっこ」や、「エア回し焼香」をするぐらいに、くすぶっている人が日本のどこかにいるんじゃないだろうか?
いいや、きっといるに違いない。
だから提案。
法事をやろう。
誰でも参加できる法事をやろう。
みんなで法事っていいじゃないか。
…よく考えると、「それはお寺の法要では?」という声があるかもしれない。
けれど、ぼくの思う法事、憧れたあの法事はお寺の法要とはちょっと違うイメージだ。
よく酒を飲むおっちゃんが「ぼうず大きくなったな!」と背中をバシバシ叩いてくるとか、おばちゃんが「こーんなちっちゃい頃から知ってるのに」と言って本人も忘れているような恥ずかしい話をし始めたり、子どもがわーわーバタバタと走り回っていたり。
子ども心になぜかそんなカオスな世界にあこがれたのだ。 「親戚の同窓会」って言葉はヘンだけどまさに、そんなイメージだ。
ぶっちゃけ、法事に参加する人は「仏事」は二の次、三の次って人が多いと思う。
どっちかというと、後の食事の方が楽しみという人が多いはずだ。
だからと言って、「法事というものは仏事が肝心で食事はおまけですよ」と、おぼうさんぶって真面目に言うのは違う。
だって、法事に食事がなかったら、たぶん参加率は下がる。
正直なところ、仏事の後の食事があるから、わいわいした雰囲気があるから、続いてきているのかなと思う。
じゃあ、反対に食事だけにしたら?…というのは極論。
それも、なんか違う。
結局のところ、お参りをして、食事をするのがいいのだ。
アメとムチ、緩急、宮川大助に花子。
考えてみれば「法事」は実に人間らしいバランスを保っている。
とにかく、そんな法事をやってみたい。
ただ、もしかすると法事というのは、家族・親戚というパーソナルな世界だからこそ成り立っているのかもしれないとも思う。
けれど、その枠を広げてみるのも面白いと思う。
お経、法話、食事の三点セットで、
親戚・家族が亡くなっていなくても参加できるもの。
集まる人は家族を越えた、色んな人。
テイストは昔からの法事のイメージ。
これから企画しようと考えているが、タイトルは仮に『大法事』とでもしておこう。
面白そうだなという方はぜひ、リアクションをよろしく。

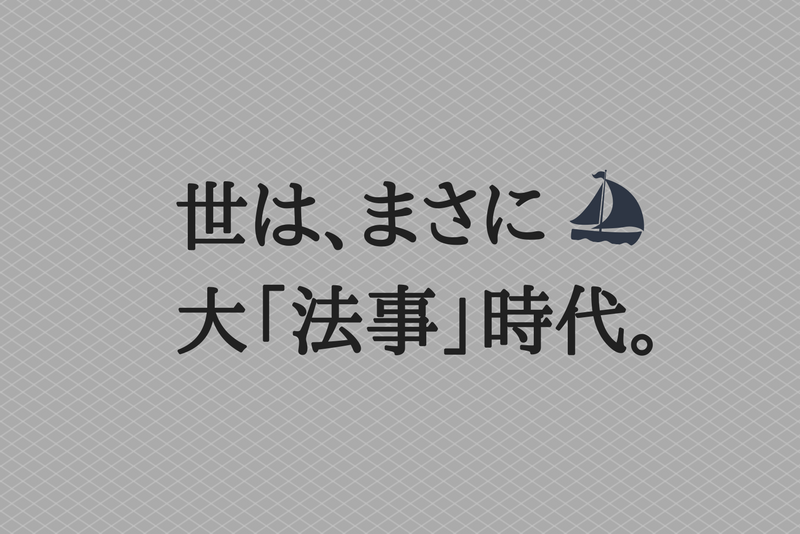
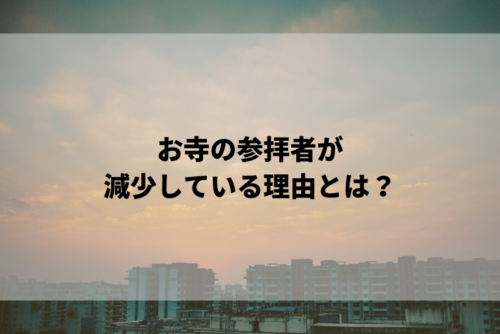
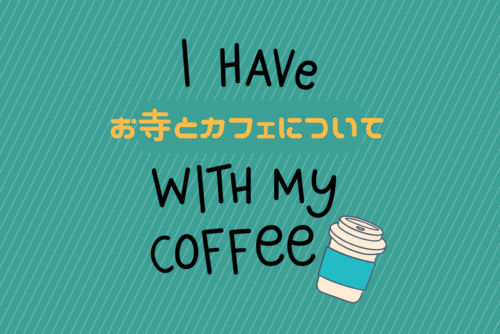
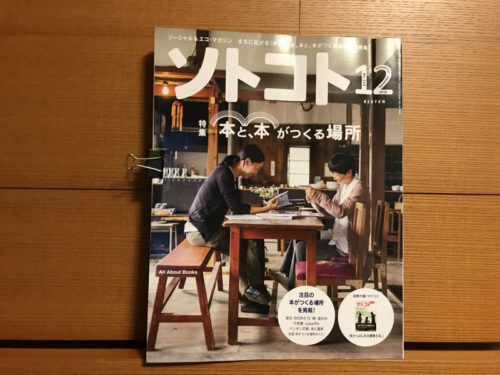



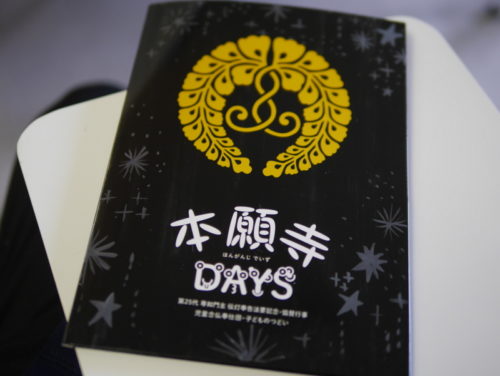
コメント